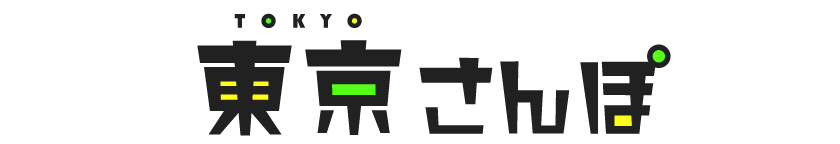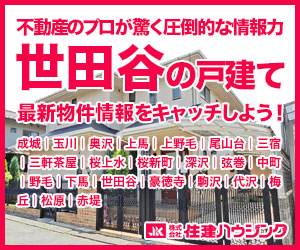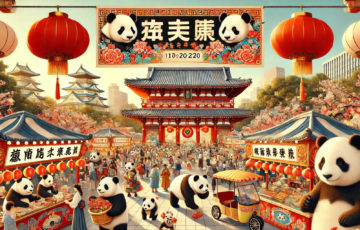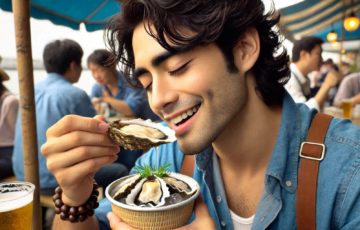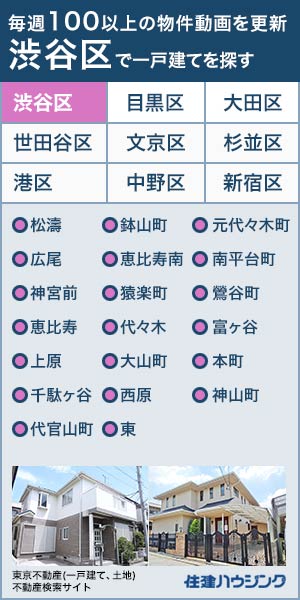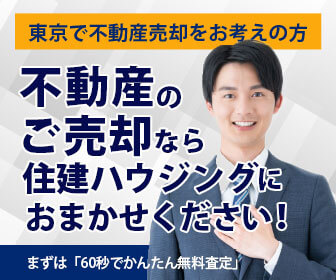江戸時代から伝わる優雅な遊戯「投扇興」をご存じですか?その魅力を存分に味わえるイベントが、浅草で開催される雅の会「投扇興の集い」です。春の観光祭の名物行事として定着したこの大会では、初心者から経験者まで幅広く楽しめる内容が盛りだくさん。扇を投げ、華麗な技や戦略で点数を競う伝統的な遊びを体験しながら、浅草の風情も満喫できる絶好の機会です。この記事では、イベントの詳細情報や楽しみ方をご紹介します。
目次
雅の会「投扇興の集い」の魅力
投扇興の歴史と文化的価値
投扇興は江戸時代中期に生まれた日本独自の遊戯です。当時の武家社会で礼儀作法や身体能力を養う手段として発展し、やがて町人にも広まりました。扇を投げて的(蝶)に当てる単純な動作ですが、その中に日本の美意識や洗練された技術が凝縮されています。雅の会「投扇興の集い」では、この伝統文化を身近に体験できる貴重な機会を提供しています。
#大河べらぼう 第9回にちなんだ浮世絵をご紹介。吉原の亡八たちが投扇興という、的に向かって扇を投げる遊びをしていましたが、花魁たちが投扇興をしている様子を描いた浮世絵がこちら。北尾重政と勝川春章による『青楼美人合姿鏡』という絵本ですが、次回に出てくるかもしれません。 pic.twitter.com/WEHvyOf37P
— 太田記念美術館 Ota Memorial Museum of Art (@ukiyoeota) March 2, 2025
イベントの特徴と見どころ
雅の会「投扇興の集い」の最大の魅力は、初心者から熟練者まで楽しめる多彩なプログラムです。競技大会では、個人戦と団体戦が行われ、参加者たちの真剣な表情と華麗な技が見られます。また、初心者向けの体験コーナーでは、専門家による丁寧な指導を受けながら、投扇興の基本を学ぶことができます。
投扇興の競技ルールと技術
基本ルールと得点システム
投扇興の基本ルールは、扇を投げて的(蝶)に当て、その倒れ方で点数を競うというものです。的は3つあり、それぞれ「松」「竹」「梅」と呼ばれます。扇が的に当たって倒れた場合、その倒れ方によって得点が決まります。例えば、的が完全に倒れて扇が上に乗った状態(これを「鶴」と呼びます)が最高得点となります。また、的が倒れずに扇が立った状態(「亀」)も高得点です。これらの基本ルールを理解することで、競技の面白さがより深まります。
今日の浅草 雅の会 投扇興と投壷の集い。投扇興のルーツと言われる投壷の映像です。こんなに入ったのは初めて見ました。 #投扇興 #asakusa pic.twitter.com/3qSY12IrRq
— 飯島邦夫 (@asakusakumasan) April 15, 2017
高度な技と戦略
投扇興は単純な運動能力だけでなく、高度な技術と戦略が要求される競技です。例えば、扇の開き方や持ち方、投げる角度や力加減など、細かな調整が必要です。また、的の配置や風の影響も考慮しなければなりません。熟練者は、これらの要素を瞬時に判断し、最適な投げ方を選択します。さらに、対戦相手の得点状況を見ながら、リスクを取るか安全に得点を重ねるかといった戦略的な判断も重要です。雅の会「投扇興の集い」では、これらの高度な技や戦略を間近で観察し、学ぶことができます。
イベント参加の楽しみ方
初心者向け体験コーナーの活用法
初めて投扇興に触れる方には、体験コーナーがおすすめです。ここでは、専門家による丁寧な指導を受けられます。扇の正しい持ち方や投げ方の基本を学び、実際に的を狙って投げる練習ができます。また、投扇興の歴史や文化的背景についても解説があり、単なる技術だけでなく、その奥深さを理解することができます。
今日の浅草。
初心者の投扇興体験はじまりました。
雅の会 投壺と投扇興の集い。
#淺草 #Asakusa #tokyo #japan #mode #fashionable pic.twitter.com/KVNG6VWY1y— 飯島邦夫 (@asakusakumasan) April 6, 2019
競技観戦のポイント
競技大会の観戦も、投扇興の魅力を知る絶好の機会です。個人戦では、選手一人一人の個性的な投げ方や戦略に注目してみましょう。団体戦では、チームワークや順番による戦略の違いなど、より複雑な駆け引きを観察できます。また、選手の所作や立ち振る舞いにも注目です。投扇興は単なる競技ではなく、礼儀作法を重んじる文化でもあります。選手たちの美しい動きや、勝敗を超えた互いの敬意を表す姿勢からも、日本文化の奥深さを感じ取ることができるでしょう。
投扇興「雅の会」2025の詳細
最寄駅 : 浅草駅
会場 : 台東区立浅草文化観光センター
日程 : 2025年4月5日(土)
公式サイト : https://www.e-asakusa.jp/
※掲載内容は変更されている場合があります。最新の情報は、会場や主催者の公式サイト等でご確認ください。