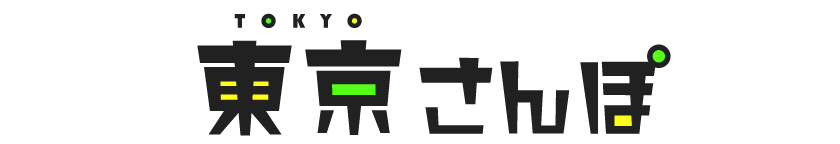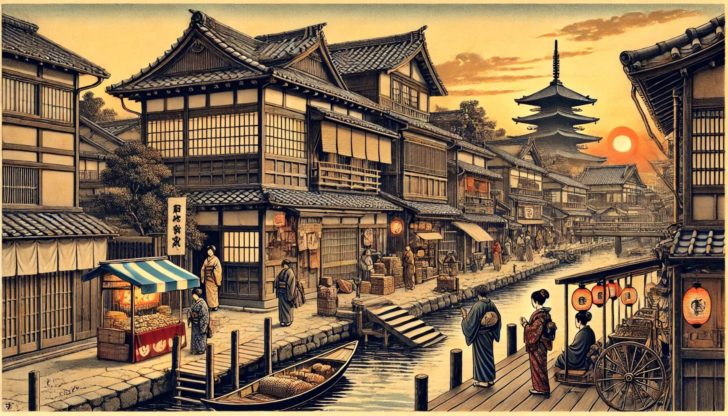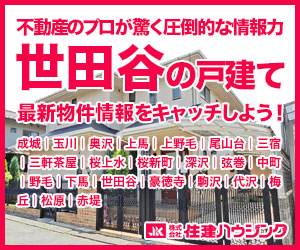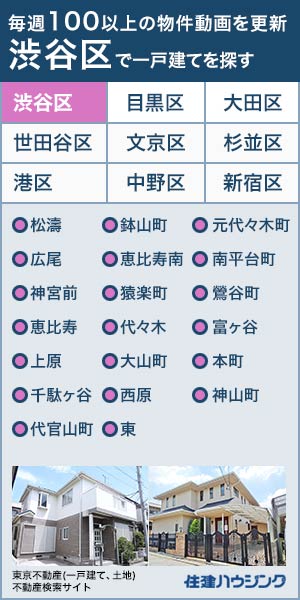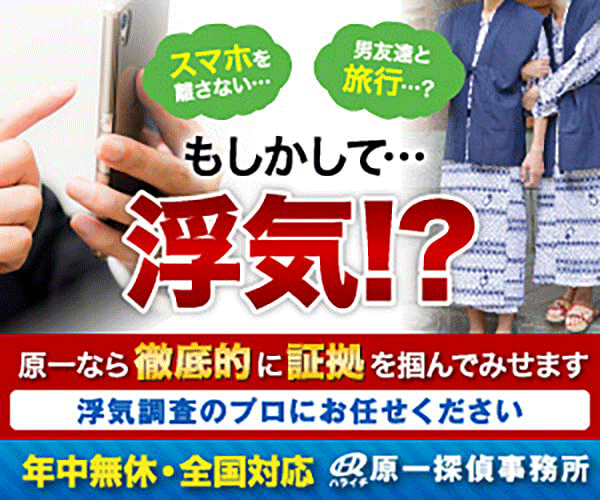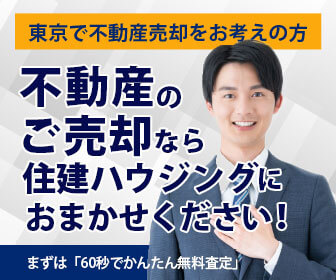市谷の地名に秘められた江戸時代の痕跡
船河原町と砂土原町:水運と土地開発の歴史
市谷船河原町(いちがやふなかわらまち)は、その名の通り船との関わりが深い地域です。徳川家康が江戸城を築く以前、この辺りは小川が作る湿地帯でした。幅広い池のような川になっていたため、船の係留に適していたことから「船溜り」「船河原」と呼ばれるようになりました。一方、市谷砂土原町(いちがやさどはらちょう)の名前には、江戸時代の土地開発の歴史が刻まれています。かつてこの地には本多正信(佐渡守)の別邸があったことから「佐渡原」と呼ばれていました。後に本多邸跡の土を採取して埋め立てに使用したことから「砂土取場」と呼ばれ、やがて「砂土原」に変化したのです。船河原町築土神社
— HAPPYMAN (@DADAMAN537407) January 27, 2025
新宿区市谷船河原町9-1
船河原町築土神社は東京・九段にある平将門を祀る築土神社の飛び地摂社です。この地には江戸時代より「堀兼(ほりがね)の井」と呼ばれる井戸があり、幼い子どもを酷使して掘らせたと伝えられるが現在はありません。 pic.twitter.com/UF1WIzE4GE
今日の #どうする家康 ではすっかり家康の参謀役に収まってしまった本田正信でしたが、彼は江戸に行った後、現在のJR市ヶ谷駅近くに屋敷をもらったといわれています。その場所が新宿区市谷砂土原町。正信は佐渡守だったことが地名の由来とされています。 pic.twitter.com/JLelpBuONJ
— 歩き旅応援舎 (@arukitabiouen) October 1, 2023
武家屋敷と寺社が残した足跡:鷹匠町と八幡町
市谷鷹匠町(いちがやたかじょうまち)は、その名の通り江戸時代に鷹匠(鷹使い役人)の組屋敷があったことに由来します。武家社会の階級制度を反映した町名と言えるでしょう。市谷八幡町(いちがやはちまんちょう)には、江戸城の守護神として重要な役割を果たした神社の歴史が刻まれています。1479年に太田道灌が鎌倉の鶴岡八幡を勧請して創建された神社は、江戸時代に市谷に移され、市谷八幡となりました。さらに、この神社の鳥居そばには幕府公認の「時の鐘」があり、江戸の町に時を知らせる重要な役割を果たしていました。江戸八所八幡宮巡り⑥
— オイラ (@oirajyunrei) February 17, 2025
市谷亀岡八幡宮⛩️(新宿区市谷八幡町)
鶴に対して亀🐢
太田道灌が江戸城の守護神として鶴岡八幡宮の分霊を祀ったのが起源
歌川広重の名所江戸百景「市ヶ谷八幡」でも描かれ御朱印帳もそれがモチーフになってます📙
御朱印は書置きで境内の茶ノ木稲荷神社のもいただけます💁 pic.twitter.com/ljP1ppOscZ
明治以降の変遷と現代に残る歴史の痕跡
町名変更と区画整理:左内町と柳町の例
市谷左内町(いちがやさないちょう)の名前の変遷は、江戸から明治への移行期の様子を物語っています。当初は坂町と呼ばれていましたが、名主の島田佐内にちなんで佐内坂町となり、最終的に明治末期に坂を略して佐内町となりました。市谷柳町(いちがややなぎちょう)は、明治4年に複数の地域が合併してできた町です。寛文年間(1661年~)には既に町屋があり、川田ヶ窪町と呼ばれていた地域と、清内屋敷と呼ばれていた地域が統合されて現在の町名になりました。柳町の由来については諸説ありますが、地形や植生の特徴を反映した名前である可能性が高いでしょう。この町、風情があります。かつての夜学で学んだ時代を思い出しつつ… #市ヶ谷 江戸時代初期に坂上周辺の町屋と共に開発された坂。名主島田佐内が草創。町名が左内坂町、坂道が左内坂。 pic.twitter.com/Bes5unNii1
— Manami Tamagawa (@Infinivalue) September 18, 2018
[江戸の店]216
— 大森博子 Hiroko Ohmori🔍📚 (@11111hiromorinn) April 2, 2020
市ヶ谷柳町(右の店):古くは豊島郡野方領市谷村に属し、俗に「川田ヶ窪(久保)」と称していた地域の一画。寛文(1661~1672年)以前には既に町屋があり、大久保通りの北側は「川田ヶ窪(久保)」、南側は「柳町」と俗称されていた。1713(正徳3)年に江戸町奉行支配となり市ヶ谷柳町に。 pic.twitter.com/rAGm5gOFat
現代に残る歴史的建造物と跡地
市谷本村町(いちがやほんむらちょう)には、江戸時代の大名屋敷の面影が今も残されています。かつてこの地にあった尾張藩二代徳川光友の上屋敷跡は、現在の陸上自衛隊市谷駐屯地となっています。江戸時代には「楽々園」と呼ばれる名庭園があったそうで、当時の繁栄を偲ばせます。市谷山伏町(いちがややまぶしちょう)には、江戸初期の著名な儒学者・林羅山の墓所が残されています。約360㎡の敷地内には、羅山をはじめ代々の当主とその家族の墓約80基が現存しており、中でも儒葬と呼ばれる珍しい様式の墓石が4基あることで知られています。これらの史跡は、江戸時代の学問と文化の中心地としての市谷の役割を今に伝えています。
市谷の町名は、江戸時代から現代に至るまでの東京の歴史と文化を凝縮して伝えてくれます。水運、武家文化、宗教、学問など、多様な要素が織り込まれた町名の由来を知ることで、私たちは過去の東京の姿をより鮮明に想像することができるのです。これらの町名は、急速に変化する都市の中で、貴重な歴史の証人として今も静かに息づいています。新宿区市谷山伏町1丁目の林氏墓地。 pic.twitter.com/mCKsruLCU8
— A.Tabata (@otorchan) May 28, 2023
市谷の町名に秘められた歴史と文化
市谷加賀町:加賀藩の足跡を今に伝える
市谷加賀町(いちがやかがちょう)は、江戸時代前期に加賀藩主・前田光高夫人(徳川家光の養女大姫)の屋敷があったことに由来します。明暦2年(1656年)に大姫が亡くなった後、屋敷地は幕府によって収公され、多くの旗本に分割されました。現在、この地域には大日本印刷本社や緑地「市ヶ谷の杜」があり、江戸時代の面影を残しつつ、現代の企業活動と調和した街並みを形成しています。市谷の杜 本と活字館
— 旅とクラフト (@AMFFCRAFTWORK) June 1, 2024
市ヶ谷にこんな素敵な施設がオープンしているとは知りませんでした。
ここに印刷工場が造られたのは1886年。1935年に合併して大日本印刷株式会社となりました。この建物は1926年に建てられ、2016年まで社屋として使われていました。
現在、活版印刷などの展示を無料で見学できます pic.twitter.com/euwlnYJv2j
市谷甲良町:江戸の匠の記憶
市谷甲良町(いちがやこうらちょう)は、幕府の作事方棟梁を務めた甲良氏の屋敷地があったことに由来します。江戸時代の建築技術の中心地として栄えた歴史が、この町名に刻まれています。いつの間にか復活した試衛館跡の碑。幕末のスター、新選組はこの試衛館から始まった。江戸の甲良屋敷(現在の市谷甲良町の地名の由来になった)に間借りしていたという。歴史研究者でもその位置は異論があり定まっていなかった。大河ドラマ放送を機に設定。立て札ができ、撤去、移動、再設置を繰返す。 pic.twitter.com/69JmT6VnhS
— 甲野功@あじさい鍼灸マッサージ治療院 (@kouno_isao) February 4, 2025
市谷台町と市谷田町:地形と開発の歴史
市谷台町(いちがやだいまち)は、その名の通り台地に位置していることから名付けられました。一方、市谷田町(いちがやたまち)は、かつての水田地帯を埋め立てて開発されたことに由来します。これらの町名は、江戸時代から明治期にかけての土地利用の変遷を物語っています。『路傍の石』で知られる文豪 #山本有三(1974年1月11日没)は1924年~26年、市谷台町(現在の新宿区)に在住しました。その後は文筆業の傍ら、児童教育にも注力。長岡藩での学校設立の故事を基に、書き下ろした戯曲が『米百俵』です。“未来を担う新しい世代を育む思想”を現代に伝えています。#一一一忌 pic.twitter.com/HuzX3OKQtY
— 古城まさお|東京都議会議員|新宿区|公明党 (@kojomasao) January 10, 2025
市谷長延寺町:寺院の歴史と現代の変容
市谷長延寺町(いちがやちょうえんじまち)は、かつてこの地にあった長延寺という寺院に由来します。明治中頃に寺院は杉並区和田に移転し、現在その跡地は都営長延寺アパートとなっています。寺院の名を冠した町名が残る一方で、土地利用の形態は大きく変化しており、江戸から現代への移り変わりを象徴しています。市谷長延寺町、都営長延寺アパート。ほぼ袋小路状の谷道のつきあたりに3棟の集合住宅が並ぶ。周囲の崖沿い約5mほどの高さににぐるりと通路がめぐっているが、動線上あまり有効と思えないその通路に不釣り合いなほど幅が広く、それを支える擁壁も頑丈につくってある謎。 pic.twitter.com/WBYRScOFJy
— 吉野 忍 (@FUKUBLOG) July 17, 2020
市谷仲之町:地理的位置関係が生んだ町名
市谷仲之町(いちがやなかのちょう)は、その名が示すように、周辺の町々の「中間」に位置することから名付けられたと考えられます。江戸時代の地理感覚や町割りの名残を今に伝える町名です。住吉町(旧・市谷谷町):新しい時代への願い
住吉町(すみよしちょう)は、かつての市谷谷町から改称されました。「谷」という字が重なることによる混同を避け、また「住みよい」という願いを込めて、昭和27年(1952年)に町名が変更されました。この変更は、戦後の新しい時代への期待を反映しています。[町火消]34
— 大森博子 Hiroko Ohmori🔍📚 (@11111hiromorinn) August 29, 2021
六番組 お組 市谷谷町ほか 人足118人 「下り藤に駒形」
現町名:新宿区住吉町、市谷台町
→ pic.twitter.com/xHN2WeeA7B
富久町(旧・市谷冨久町):繁栄への願望
富久町の歴史は江戸時代にさかのぼり、当時は寺院地や武家地として利用されていました。1872年7月に牛込区市ヶ谷冨久町が成立し、複数の寺院地や武家地が統合されました。1983年8月の住居表示実施により、市谷冨久町の大部分と周辺地域の一部を合わせて現在の富久町が誕生しました。この際、「市谷」の冠称が除かれましたが、理由は不明です。河田町(旧・市谷河田町):牛込村の名残
河田町(かわだちょう)は、もともと牛込村に由来する地名でしたが、後に市谷河田町となり、現在は「市谷」の冠称が外れています。この町名の変遷は、江戸時代から明治、そして現代に至る行政区画の変化を反映しています。市谷エリアの町名は、江戸時代の武家屋敷や寺社、地形的特徴、そして明治以降の都市開発の歴史を今に伝えています。これらの町名を通じて、私たちは東京の歴史的な重層性と、時代とともに変化しつつも伝統を守り続ける都市の姿を垣間見ることができるのです。