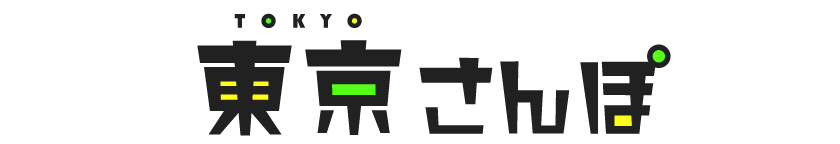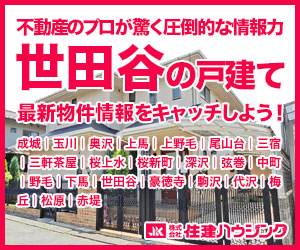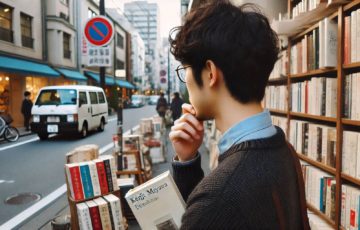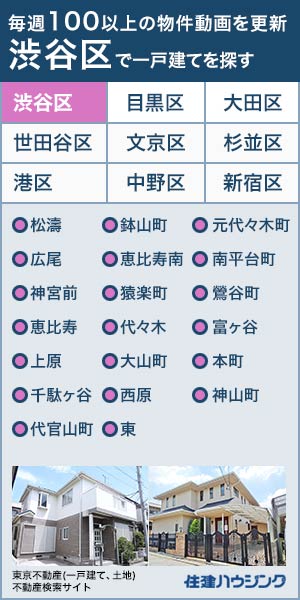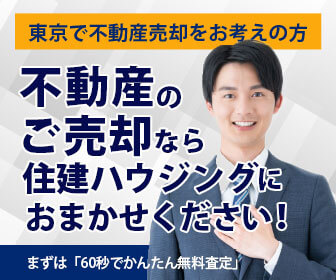目次
「置いてけぼり」の語源と本所七不思議
「置いてけぼり」の意味と由来
「置いてけぼり」は、一緒にいた人を置き去りにすることを意味する日本語表現です。約束の時間に遅れた人を待たずに先に行ってしまうことも指します。この言葉の由来は、江戸時代から伝わる本所七不思議の一つ、「置いてけ堀」(または「置行堀」)の伝説に基づいています。置いてけ堀の根付けが手に入らなかったけど、とりあえず錦糸堀公園には行ってみた
— ぺた@pkg (@peta0133) March 8, 2025
作中みたいな良い感じの曇天だっただけに非常に残念だ… pic.twitter.com/E28pi460B7
本所七不思議とは
本所七不思議は、現在の東京都墨田区(旧本所)を舞台とした奇談・怪談の集まりです。江戸時代から語り継がれ、都市伝説の一つとして、また落語の題材としても親しまれてきました。七不思議には7つ以上の話があり、「置いてけ堀」はその中でも特に有名な話の一つです。「置いてけ堀」の伝説
怪異の内容
「置いてけ堀」の伝説は次のようなものです。本所にあった堀は魚がよく釣れる場所として知られていました。しかし、釣り人が魚を釣って帰ろうとすると、どこからともなく「おいてけ~おいてけ~」という奇妙な声が聞こえてきます。この声を無視して魚を持ち帰ろうとすると、何らかの怪異に遭遇するというのです。・本所の狸(東京狸列伝其一)
— 東龍斎小虚 (@little_kyoshin) August 11, 2021
横網町だか錦糸町だかの屋敷の堀がかの「置いてけ堀」であり、夜な夜な釣り人から魚をせびっていたのは狸だという。足洗邸の怪談で敵討を手伝ったのはこの狸でしかも女狸だったらしい。今彼女は甘い人形焼に化けて腹鼓の代わりに観光客に舌鼓を打たせてやっている。 pic.twitter.com/eKKtpMpJYk
伝説のバリエーション
「置いてけ堀」の伝説には、いくつかのバリエーションがあります。多くの場合、釣り人が家に帰って魚籠を確認すると、釣った魚が消えていたというものです。より恐ろしいバージョンでは、水中から手が伸びてきて釣り人を引きずり込もうとしたり、妖怪が出現したりするというものもあります。江戸時代の浮世絵師、三代目歌川国輝の絵では、魚を置いていくよう指示する幽霊のような化け物が描かれています。「置いてけ堀」の舞台と現在
伝説の舞台とされる場所
「置いてけ堀」の舞台とされる場所には諸説あります。最も有力とされるのは、現在の錦糸町駅近くにあった「錦糸堀」です。他にも、御竹蔵(おたけぐら)周囲の堀(現在の横網一丁目および二丁目付近)なども候補地とされています。御竹蔵は江戸幕府の資材置き場で、その範囲は広大で、現在の横網町公園から江戸東京博物館、さらには両国国技館までを含む広い地域だったとされています。『本所深川奉行所 お美世のあやかし事件帖』舞台散歩
— 久真瀬敏也@2/5『お美世のあやかし事件帖』発売 (@KUMASE_TOSHIYA) February 8, 2025
錦糸町の『錦糸堀』
こちらも本所七不思議の『置いてけ堀』の舞台と言われている(※諸説あります)
本作では、表紙にもいる河童の大将・源治の住処となっている
最近、そんな堀に、河童の苦手な物が投げ込まれるという事件も起きていて… pic.twitter.com/WSWyFYUUGF
置いてけ掘(御竹蔵跡・江戸東京博物館そば)
— mayumi (@mayumi0401ab) March 18, 2018
本所割下水
堀だった所が暗渠に pic.twitter.com/VK2zGYNUmU