地名の由来 「豊島編(1)」
土地の名前は、その地域の伝説、地形、施設建物、職業、習慣など実に様々な 由来によって名付けられています。 地名の由来を知ることにより、その地の奥深い歴史に触れることでしょう。 そんな地名の楽しい由来についてご紹介致しま...
 東京おもしろ雑学
東京おもしろ雑学
 東京おもしろ雑学
東京おもしろ雑学
 東京おもしろ雑学
東京おもしろ雑学
 東京おもしろ雑学
東京おもしろ雑学
 東京おもしろ雑学
東京おもしろ雑学
 東京おもしろ雑学
東京おもしろ雑学
 東京おもしろ雑学
東京おもしろ雑学
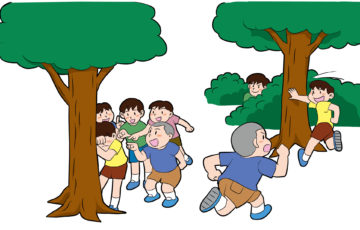 東京おもしろ雑学
東京おもしろ雑学
 東京おもしろ雑学
東京おもしろ雑学
 東京おもしろ雑学
東京おもしろ雑学
 東京おもしろ雑学
東京おもしろ雑学
 東京おもしろ雑学
東京おもしろ雑学
 東京おもしろ雑学
東京おもしろ雑学
 東京おもしろ雑学
東京おもしろ雑学
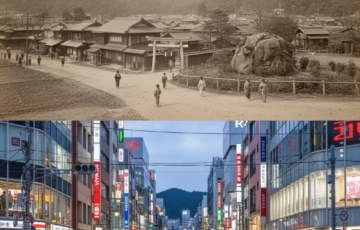 東京おもしろ雑学
東京おもしろ雑学
 東京おもしろ雑学
東京おもしろ雑学
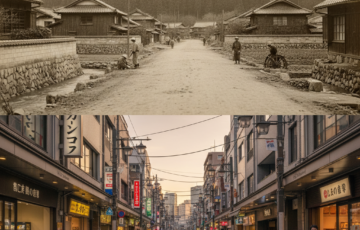 東京おもしろ雑学
東京おもしろ雑学
 東京おもしろ雑学
東京おもしろ雑学
 東京おもしろ雑学
東京おもしろ雑学
 東京おもしろ雑学
東京おもしろ雑学